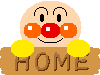�J�����kQ&A
0401
| ���_����ԓr���̑ސE�� |
�p�F�_��Ј��ł��B�_����ԓr���őސE�������̂ł����A��Ђ́u�_��s���s�v�ői����Ƌ�������܂��B
�` : �_����ԓr���ł��A�u�����ȗ��R�v������A���Ԃ̓r���ł��������ɉ��ł��܂��B
�@���R�̂��Ƃł����A��Ђ��c�Ƒ���x����Ȃ��Ȃǂ̘J��@�ᔽ���s���Ă���ꍇ�∫���ȃZ�N�n���A��p���n���Ȃǂ����ł��܂��B
�@�܂�1�N���̊��Ԃ��߂��J���_���������Ă���ꍇ�ɂ́A�J���_��̏��������N���o�߂������ȍ~�ɂ����āA�g�p�҂ɐ\���o�邱�Ƃɂ��A���ł��ސE�ł��܂��i�J��@ 137 ���@�������A���I�Z�p�ҁA��60�Έȏ�̘J���҂͏��O�j�B
�@�܂��A���ۂ̘J���������J���_��Ƒ��Ⴗ��ꍇ�ɂ����ẮA�J���҂͑����ɘJ���_����������邱�Ƃ��ł��܂��i�J��@�� 15 ��� 2 ���j�B
�@�܂��A���@ 628 ���́u��ނȂ����R�v������ꍇ�͉���F�߂Ă��܂��B�Ⴆ�Έȉ��̏ꍇ�Ȃǂ��Y�����܂��B
�@�@1. �S�g�̏�Q�A���a�ȂǁB
�@�@2. ���e��q���̕a�C�̉��ȂǁB
�@�@3. �Ɩ����@�߂Ɉᔽ���Ă��邱�ƁB
�@
0402
| ��3�N�_��Ј��̒��r�ސE�� |
Q �F�@ 3 �N�_��̎Ј��ł��B�܂� 2 �N�ł����A�ސE����]������_��ᔽ���Ɠ{���܂����B��P�N�䖝���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��傤���B
A �F �䖝���邱�Ƃ͂���܂���B�J��@�� 14 ���P���ł͗L���J���_��̌_����Ԃ̏���� 3 �N�Ƃ���Ă��܂��B�������A���@ 137 ���ɂ��P�N�����_������ԘJ���҂ɑ��āA�u�J���_��̊��Ԃ̏�������P�N���o�߂������ȍ~�ɂ����ẮA�g�p�҂ɐ\���o�邱�Ƃɂ��A���ł��ސE���邱�Ƃ��ł��܂��v�i���I�Z�p�҂▞ 60 �Έȏ�̘J���҂͏����܂��j�ƂȂ��Ă��܂��B���Ȃ��͂��ł��ސE�ł��܂��B�䖝���邱�Ƃ͂���܂���B
�@�܂��A���@ 628 ���́u��ނȂ����R�v������ꍇ�͉���F�߂Ă��܂��i Q0401 �Q�Ɓj�B
�@�������A�����҂̈���ɉߎ����������ꍇ�͑�����ɑ��Q�����̐ӔC���܂��B
0403
| ���ސE�������̂ɋ����ł�߂����Ă���Ȃ��� |
�p�F �Α� 5 �N�A���Ј��B 2 �����O�ɑސE�肢���o�����̂ɁA�В������߂����Ă���܂���B�\�͓I�ɋ����܂����̂��Ƃ����Ă��܂��B�ǂ̂悤�ȕ��@���Ƃ�ΑސE�ł��܂����H
�`�F�ٗp�����̂Ȃ���ʂ̎Ј��̏ꍇ���ސE���鎞�́A�@�I�ɂ́A�ސE�͂��@ 628 ���̋K��ɏ]���Q�T�ԑO�ɒʒm����悢���ƂɂȂ��Ă��܂��B�����đސE�������I�ɂ����Ȃ��ȂǂƂ������Ƃ́A�E�ƑI���̎��R�Ɉᔽ���A�܂������J���ƂȂ��@�s�ׂƂȂ�܂��̂ŁA���X�ƑސE�͂��o���ĉ������B�ސE�͔͂z�B�ؖ��t���e�ؖ��X�ւ𗘗p����Ƃ����ʂ�����Ǝv���܂��B
�@�܂��A�ٗp�����̂���_��Ј��̏ꍇ�͑o�����̊����܂Ō_�����邱�Ƃ͊�{�����ł����A��Б��ɃZ�N�n����c�Ƒ�x�������ۂȂǂ̘J��@�ᔽ������ꍇ�́A���������_������Ȃ��͉̂�ЂƂ������ƂɂȂ�܂�����A�_����Ԃ̓r���Ō_��ᔽ�Ƃ��ĉ�Ă����܂��܂���B
0404
| ���u�ǂ����Ă����߂�̂ł���Β������قɂ���v�Ƃ���ꂽ�� |
�p�F���͐��Ј��Ƃ��Čٗp����Ă��܂����A��Ђ����߂悤�Ǝv���A�A�ƋK���ɒ�߂Ă���ʂ�P�����O�Ɏ��\���o���܂������ސE��F�߂Ă���܂���B����ǂ��납�В��́u�ǂ����Ă����߂�̂ł���Β������قɂ���v�Ƃ����č����Ă���܂��B���̗l�Ȃ��Ƃ͂ł���̂ł��傤���H
�`�F �ł��܂���B���������В��������Ă��邱�Ǝ��́A���@�ŔF�߂��Ă���u�E�ƑI���̎��R�v��N�Q���Ă��܂��B
�@�܂��A�J���_��@ 15 ���ɂ�茠���̗��p�Ƃ��Ė����Ɣ��f����܂��B
�@���Ј��i�ٗp�_����Ԃ̂Ȃ��J���ҁj�̏ꍇ�A�����A�ƋK���Ɂu��Ђ��ސE��F�߂��ꍇ�v�Ƃ��u�U�����O�Ɏ��\���o�����Ɓv������߂��Ă����Ƃ��Ă��A�O�q�Ɠ��l�ɖ����ƂȂ�܂��B
0405
| ���ˑR���Ȃ��Ɍ�������������Ă�����-���̂P-�� |
�@���⌨�������̂������獷���ʁB�����ƌ���ꂽ��A�u�ސE�͓��R�v�ƌ�������ɖ����������Ă�����A�����ȓ]�ЁA�o���A�s����Ȃ��Ƃ킩���Ă�����ł̒n���z�]�A���Ȃǂ����Ȍ`�őސE�𔗂��Ă��܂��B
�@�܂����Ă����Ȃ����Ƃ́A���̏�ŏ������Ȃ����ƁB�u�͂��A�킩��܂����B�v�Ȃǂƌ����Č���Ȃ��B���ނɃT�C�����ӂ͉����Ȃ����ƁB����͕��C�Ŏ����S�������Ă��܂��B����ł��������ɂȂ�Ȃ����ƁB���̏�͒f�邱�Ƃ���ł��B���������u�l�������ĉ������ȂǂƁv�Ƃ��̏�Ŋm��I�ȕԓ�������A���f�𗯕ۂ��邱�Ƃ���ł��B�ŏ��̂��Ȃ��̑Ή����A���̌�̘b���̕�����傫�����E���Ă��܂��܂��B
�@���������A���ق͘J���_��@�P�U���̋K��ɂ��A�u�q�ϓI�ɍ����I�ȗ��R�������A�Љ�ʔO�㑊���ł���ƔF�߂��Ȃ��ꍇ�́A���̌����𗔗p�������̂Ƃ��āA�����Ƃ���B�v�ƋK�肳��Ă��܂��B�قƂ�ǂ̃P�[�X�͘J���_��@��@�Ɣ��f����܂��B
0406
| ���ˑR���Ȃ��Ɍ�������������Ă�����--���̂Q--�� |
�@�ŋ߂̘b�B���q�Ј���j�q�Ј����������͂�ŁA�ސE�͂Ɉ�ӂ����������Ƃ������Ƃ�����܂����B��ϕ����������s�ׂł����A�����ɂȂ�Ƃ��߂����b�ł�����܂��B����Ȏ��͌x�@���ĂԂ��炢�̋C�������K�v�ł��B
�@ �Ƃɂ����A�ސE�͓��ɂ̓T�C�����Ȃ��B��ӂ������Ȃ��B���ꂪ�̐S�ł��B���ꂩ��ƂɋA���ė�Âɍl���܂��傤�B
�@
�܂���l�����ōl�����A�Ƒ���M���ł���l�ɑ��k���邱�Ƃ���ł��B�܂��A���I�@�ւ�j�I���i��l�ł������ł���J���g���j�ȂǂɎx���������Ƃ���̕��@�ł��B
�@�@���Ɉᔽ����s�ׂɂ͋����Ȃ��C������ł��B
0407
| ���ˑR���Ȃ��Ɍ�������������Ă�����--���̂R--�� |
�@�ƂɋA���čl���܂��傤�B
�@�Ƃɂ������ق͊ȒP�ɂł��܂���B
�@�J���_��@�ɂ��A�����I�ȗ��R���Ȃ���Ή��ق͌����̗��p�Ƃ��F�߂�@��܂���B�܂��A���C�I�t�̏ꍇ�́u�������ق̂S�v���v�i�ō��ٔ����j���m������Ă���A�����S���������Ȃ���Ȃ�܂���B�����̗v���ɊY�����Ȃ��ꍇ�͉��ق͂ł��܂���B
�@�i���j�������ق̂S�v���͈ȉ��̂Ƃ���ł����A�i���ڂ̏ڍׂȓ��e�͂��Ȃ茵��������Ă��܂��B
�@�@�@�P�D�s����o�c��@�Ȃǂɂ���Čo�c��A�l���팸�ɏ\���ȕK�v�������邩�B
�@�@�@�Q�D���ق�������邽�߂ɁA��Ђ͂�����w�͋`�����\���s���������B
�@�@�@�R�D���ّΏێ҂̐l�I���q�ϓI�A�����I�Ȋ�Ɋ�Â������ɑI�肳��Ă��邩�B
�@�@�@�S�D�J���g�����͘J���҂ɑ��Đ������ق̕K�v���Ɛl���팸�̓��e�i�����E�K�́E���@�j�ɂ��ď\���������A���Ӂ@�@�@�@�@�������ċ��c�������B
0408
| ���ˑR���Ȃ��Ɍ�������������Ă�����--����4--�� |
�@�O���̐������ق̂S�v���������̏ꍇ�ɓ��Ă͂߂āA�m�F���܂��傤�B�ǂ�����Ă͂܂�Ȃ��Ǝv����ꍇ�́A�f�����̗v�ł��B
�@�܂��A�M����l�őR�ł��܂����B�����E��œ�������ɂ�����Ă��铯����������A�ꏏ�ɓ����邩�ǂ����A�������Ă݂܂��傤�B��l�œ������A��l�ł������ق����͂����{�ɂ��Ȃ�܂��B�ł������Ĉ�l�ł������Ȃ��킯�ł���܂���B
�@���j�I���ƌ����Ĉ�l�ł������g�����e�n��ɂ���܂��B�o���邾�����l�őg�����ɂȂ邱�Ƃ��悢�̂ł����A�ł���l�ł����v�ł��B�g���ɂ͂���L�����͈ȉ��̂悤�ȓ_������܂��B�����A
�@�@�@�@�@���j�I���ɂ͌��@�ŕۏႳ��Ă���c�̌������̘J���O�������邱�ƁB
�@�@�@�A�@�g�����ɂȂ邱�Ƃɂ���ĘJ���g���@�̕ی�����邱�ƁB
�@�@�@�B�@���j�I���ɓ��邱�Ƃɂ���āA����܂ŘJ���g���ɒ~�ς��ꂽ�o������������邱�ƁB
�@�@�@�C�@�o���ɗ��ł����ꂽ���X�^�b�t���A���k�E�w�����Ă���邱�ƁB
�@�@�@�D�@�ꍇ�ɂ���čR�c�s�����K�v�ȏꍇ�́A�E��ł͈�l�ł��A���j�I���̑��̐E��̑g��������ٓ��ŎQ�����Ă���@�@�@�@�@�@���ƁB
�@�@�@�E�@��l�ł͗����������Ȃ������g�p�҂ɑ��āA�c�̌��ɂ���āA��@�s�ׂɑ��ē��X�Ɖ��P�����߂邱�Ƃ��ł��@�@�@�@�@�@�邱�ƁB
0409
| �����Ɣ��~�`���� |
�p�F��Ђ�ސE���ē��Ƒ��ЂɏA�E���悤�Ǝv���Ă���̂ł����A���݂̉�Ђ��瓯�Ƒ��ЂɏA�E����̂ł���ΑސE�����x����Ȃ����A�i����ƌ����Ă��܂��B����Ȏ����������̂ł��傤���H
�`�F�@���I�ɂ����Ɓu�E�ƑI���̎��R�v�Ɓu���Ɣ��~�`���v�Ƃ̌��ˍ����ɂȂ�܂��B
�@���̂悤�ȏꍇ�A�ٗp�_��A�ƋK�����ɓ��Ƒ��Ђւ̏A�E�Ɋւ��āA�������̋K�������邩�ǂ����Ƃ������Ƃ��܂��ŏ��̔��f��ƂȂ�܂��B�܂��A�A�ƋK�����ɂ��̂悤�ȋK�肪�������Ƃ��Ă��A���̘J���҂��s���Ă����Ɩ��̓��e�A���Ƒ��Ђւ̏A�E���~�߂���Ԃ̒����A���ق̒��x�ɂ���ċK���͖����Ƃ���邱�Ƃ�����܂��B
0410
| ���ސE��̋����Ǝ�ւ̏A�Ƌ֎~�� |
Q: �u������Ђ̌���J���҂ł��B�ސE��\�����ꂽ���Ђ���ސE��R�N�Ԃ͉�ЂƋ�������Ǝ�ɏA���Ȃ��Ɛ��ɃT�C������Ɣ����Ă��܂��B�E�ƑI���̎��R��Ƃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�ǂ������炢���ł��傤���v
A: ���Ɣ��~�`���̌_��͖������ɋ�������ł͂���܂���B
�@�J���҂ɑ���ސE��̋������Ђւ̏A�E�K���́A�K�����J���҂̌��@22 ���̐E�ƑI���̎��R��s���ɐ��邱�Ƃ̂Ȃ��悤�ɁA�K���̑Ώۂ������ɂ��Ă��܂��B�K���̑ΏۂƂȂ肤��̂́A�u��Ƌ@����m�蓾�闧��ɂ���ҁv�Ɍ����܂��B
�@���Ȃ킿�A�Z�p�̒������̐E���A�u�c�Ɣ閧��m�蓾�闧��ɂ���v�c�ƒS���Ј����ł��B��ʂ̒P���J���ɏ]������J���҂ɂ͋K���͂ł��܂���B
�@�������A�K���̑Ώێ҂ł����Ă��A���̋`�����ꍇ�Ƃ́A���炩���߁A���Ў��̍ŏ�����u�J���_��v��u�A�ƋK���v�u�J������v�ɖ����Ȓ�߂��Ȃ���Ȃ�܂���B
�@�܂��A�ȉ��ɂ���悤�ȗv�������ď��߂ĔF�߂���Ƃ������Ⴊ����܂��B
�@�@�@�i�P�j���Ɣ��~�`����K�v�Ƃ��鍇���I�ȗ��R�B
�@�@�@�i�Q�j���Ɣ��~�`���̕K�v�����͈͂ł̂ݍ��ӂ��Ȃ���Ă���B
�@�@�@�i�R�j�����Ȏ葱�B
�@�@�@�i�S�j�֎~�Ɍ����������ȑΉ��̑��݁B
�@�]���āA���ۂɋ��Ɣ��~�`���̌_�u�L���v�ɂȂ�ꍇ�͏�ŏЉ���@ �����ȏ������K�v�ł��B
�@
0411
| ���_�����ꂸ�Ɏ��߂�Ȃ狋����Ԃ��Ɖ�ЂɌ���ꂽ�� |
�@�@�@
Q: �c�ƈ��ł��B�_��{�����܂���ł����B���Ƃ̓s���őސE�͂��o�����Ƃ���A��Ђ���u�_�����炸�Ɏ��߂�Ȃ獡�܂ł̋�����Ԃ��Ă��炤�v�ƌ����܂����B
A: �u�_����Ƃ炸�}�Ɏ��߂�ꍇ�͋�����Ԋҁv�ȂǂƂ������Ƃ��A��Ђ̏A�ƋK���ɒ�߂��Ă��邩�ǂ������܂��m�F���Ă��������B������߂��Ă��Ȃ��̂Ȃ�A��Б����u������Ԃ��v�ƌ����Ă��Ă����̍������Ȃ��b�Ȃ̂ŁA�ʏ�̑ސE�葱�����Ƃ�ꂽ�炢���Ǝv���܂��B
�@�l�����Ȃ����Ƃł����A�{���ɒ�߂Ă������ꍇ�ł��B���ꂪ�J���҂̑ސE�𑫎~�߂����邽�߂Ȃ�J����@�i�J��@�j�P�U���ɋK�肳��Ă���u�����┅���\��̋֎~�v�Ɉᔽ���܂��B
�@���炩���ߋ��z���߂ĉߑӋ��┱�����Ƃ�Ƃ������x���߂邱�Ƃ͈�@�ɂȂ�܂��B���邢�͂��ꂪ���炩�̃y�i���e�B�[�Ƃ��ĉۂ��Ă���Ƃ��Ă��J��@�X�P���́u�������فv�̋K��Ɉᔽ���܂��B
�@�J��@�X�Q���Łu�A�ƋK���́A�@�߂܂��͘J������ɔ����Ă͂Ȃ�Ȃ��v�ƒ�߂Ă���悤�ɁA����́u�@�߁��J�����A�ƋK���v�ł��B�܂�J��@�Ɉᔽ���Ă���A�ƋK���͖����ł��B
�@���Ȃ������������̋����͒����Ƃ��đS�z�x�����Ă��炤����������܂��B���ɂ��Ȃ����ސE���邱�Ƃő��Q�����������Ɖ�Б����咣�����Ƃ��Ă��A���Q�������ƒ����x�������E���邱�Ƃ͋�����܂���i�J��@�Q�S���j�B����������ƒ������x����Ȃ��ꍇ�́A��Ђ̏��ݒn���NJ�����J����ē��Ɂu�J��@�ᔽ�\�����v���o���A�����[�u���Ƃ��Ă��炢�܂��傤�B
�@�������x�����������ʼn�Б������߂đ��Q���������Ȃ��ɐ������Ă����ꍇ�A�ٔ��ŏ��Ă邩�����邩�͏ڍׂ��킩��Ȃ��̂ň�T�ɂ͌����܂���B�����A����������Б������Q���������Ȃ��ɐ������邽�߂ɕK�v�ȑސE�Ƒ��Q�̔����Ƃ̈��ʊW�A���Q�����͈̔͂Ȃǂ͍ٔ���Ŏ咣�A�����邱�Ƃ͋ɂ߂č���Ǝv���܂��B
�@�O�̂��ߘJ���ґ��̗���Ŋ������Ă���ٌ�m�i���{�J���ٌ�c�j�̖����d�b���k���������L�ɏЉ�܂��B��낵����Α��k���Ă��������B
�@�@ ���{�J���ٌ�c�i�����j�@
�@�@ �d�b�@�O�R�|�R�Q�T�P�|�T�R�U�R�y�тT�R�U�S
�@�@ ��t�@���T���j���A�Ηj���Ɩؗj���ߌ�R������ߌ�U��
�@�@���T�y�j���@�ߌ�1���`�ߌ�4���@���������y�j���́u03-3251-5363�v�̂݁j
�@��L�ȊO�̊e�n��ɂ�����܂��̂ŁA�C���^�[�l�b�g�ł����������B�@�@
0412
| �������[����t����Ȃ��� |
Q: �������ׂł͐ŋ���Љ�ی�������������Ă���̂ł����A���ۂ͕����Ă��Ȃ��悤�Ȃ̂ł��B�m���߂����ĉ�Ђ̐ŗ��m�Ɍ����[�̌�t�����߂܂������A���܂ł��o���Ă���܂���B�ǂ������炢���ł��傤���B
A: �����[����t����Ȃ��ꍇ�A��Ђ��NJ�����Ŗ����ɁA�����Ŗ@�� �Q�Q�U���Ɋ�Â������[�s��t�̓͏o�����Ă��������B���^�������茳�ɂ���ꍇ�͋��^�����̎ʂ������킹�Ď��Q���Ă��������B
�@�ڍׂ́A���ڐŖ����ɂ��₢���킹���������B�X���Ő������鎖���\�Ȕ��ł��B
�@�Z���ŁE�ٗp�ی������^����V�������Ă���ɂ�������炸�A�[�t���Ă��Ȃ��̂������ł���A�s�������ɂȂ�܂��B�ԊҐ������Ă��������B
�@���̂悤�Ȑŗ��m�����݂���Ȃ�A�ŗ��m�@�ɂ�蒦����������Ă��s�v�c�ł͂���܂���B
0413
| ���Г�3���Ԑ�ɔz�]���߁A�ސE����������Гs���ސE�ƂȂ邩�H�� |
Q: ��Ђ���z�]���߂��ł܂����B�Г��R���Ԑ�̉c�Ə��ł��B���̓I�ɖ������Ɣ��f���đސE���邱�Ƃɂ��܂����B��Ђɒʍ������Ƃ��뎩�ȓs���ސE���Ƃ����܂����B���Ƃ��Ă͔z�]���߂��_�@�̑ސE�ł��̂œ��R��Гs���ސE�ƂȂ�Ǝv���Ă��܂����B�ٗp�ی��Ƃ̊W�ő��}�ɂ͂����肳�������ł��B
A: �ٗp�ی��ɂ́A��ЂɑސE�̌��������闣�E�҂��u������i�ҁv�Ƃ��鐧�x������܂��B
�@�u������i�ҁv�Ƃ́A���ȓs���ސE�ƈقȂ�A�R�����Ԃ̑Ҋ����Ԃ��Ȃ��A�����苋�t�������������Ƃ������ł��B
�@�u������i�ҁv�̗v���̒��ɂ͉��قȂǂ̑��ɁA�u���u�n�ւ̔z�]�𖽂����Ēʋ�����ƂȂ�ސE�����ҁv���Y�����܂��B
�@���̏ꍇ�͕Г��Q���Ԉȏ����Ƃ��Ă��܂��B�ł�����{���̏ꍇ�͓��R�u��Гs���ސE�v�ƂȂ�܂��B
�@���E�[�̖{�l�L�ڗ��Ɂu�ʋ���Ȕz�u�]���̂��ߑސE�v�ƋL�ڂ��A������i�҂ɊY�����邱�Ƃ��n���[���[�N�̑��k���ɋ����咣���ĉ������B�A���A�v���Ƃ��Ĕ�ی��Ҋ��Ԃ����E�O 1 �N�Ԃ� 6 �����ȏ゠�邱�Ƃ��K�v�ł��B
�@�܂��u������i�ҁv�̑��̗v���Ƃ��ẮA���̂悤�ȏꍇ�ɗ��E�������̂��Y�����܂��B
�@�@�@�P�D�|�Y�Ȃǁ@
�@�@�@�Q�D���Ə��̔p�~�i�����܂ށj�@
�@�@�@�R�D���Ə��̈ړ]�ɂ��ʋ�����ɂȂ�����
�@�@�@�S�D���ف@
�@�@�@�T�D�̗p���ɖ������ꂽ�J�������������ƒ��������Ⴕ�����Ɓ@
�@�@�@�U�D�����z�� 3 ���� 1 ����z���x�����Ȃ����������Q�����ɂȂ�������
�@�@�@�V�D�J���҂̐E��]���Ȃǂɍۂ��āA�E�Ɛ����̌p���̂��߂ɕK�v�ȑ[�u���u���Ȃ��������Ɓ@
�@�@�@�W�D������ 85 �������ɒቺ�������Ɓ@
�@ �@ �X�D���ԊO�J������ 45 ���Ԉȏ�i���E���O�R�����ԁj���������Ɓ@
�@�@�@10 �D���Ԃ̒�߂̂���_��X�V���R�N�ȏ�o�����Čٗp�����Ɏ������ꍇ�ɂ����āA�_�X�V����Ȃ��Ȃ����ꍇ
�@�@�@11 �D��i�E�������璘���������点�������i�Z�N�n�� �A�p���n�������܂ށj���Ɓ@
�@�@�@12 �D��Ђ��璼�ځE�Ԑڂ̑ސE���������ꂽ���Ɓ@
�@�@�@13 �D��Гs���̋x�Ƃ��R�����ȏ㑱�������Ɓ@
�@�@�@14 �D��Ђ��d���̏�Ŗ@���ᔽ�����Ă��邽�߁@
�@�܂��A���l�̐��x�Ɂu���藝�R���E�ҁv�Ƃ������x������܂��B���̎��i�v�����m�F���Ă����܂��傤�B
0414�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
| ���ސE�Ɋւ��鐾�� |
Q: �̗p���ꂽ�Ƃ��ɁA�ȉ��̓��e�́u���v�Ɓu�m�v�Ƃ���������n���ꂽ�̂ł����A�܂��L�����Ă���܂���B
�@�@�u�m�v
���ȓs���őސE����Ƃ��́A 90 ���O�ɓ͂����o���A���������o�R���A�В��Ɏ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̋K������A 90 �������őސE����ꍇ�́A�e��蓖�A�ܗ^���O�� �����ɂ����̂ڂ��āA��̊z�S�z��ސE������Ɏx��������K��ɓ��ӂ���B
�@�@�u���v
�ٗp�_�������A�U�����̊��Ԓ��Ɏ��ȓs���ɂ��ސE�܂��͕s�K�ȍs���ɂ��A��Ђɑ���ȑ��Q���������ސE�i���فj�����ꍇ�́A�_�������O�����Ԃ̌��N�ی����A�����N���̊�ƕ��S�����z���x�������ƁA�܂��_��������N�ȓ��ɑސE�����ꍇ�́A���C���̉�Е��S���̌��C�������S�z�x�����܂��B
90 ���ȓ��ɎВ��̎�����Ȃ��őސE�����ꍇ�́A���̓��ɑ����錎�̎Љ�ی����̑S�z�i�o�c�ҕ��S���܂ށj���x�������Ƃ���ь_�������O�����Ԃ̌��N�ی�����ސE��ꃖ���ȓ��Ɏx�����܂��B
���̂悤�ȕ����͖��Ȃ��̂ł��傤���B
A: �m��������@�ȓ��e�̏ꍇ�́A�����ƂȂ�܂��B���ׂĖ@�����D�悳��܂��B
�@�@���ł͖��@ 627 ���̋K��ɂ��A�ސE�͂Q�T�ԑO�ɓ͂���A�L���ƂȂ�܂��B
�@��Ђ��X�O���O�ɓ͂��Ăق����ƎЈ��ɗv�]���邱�Ƃ͎��R�ł����A 90 ���@�����őސE�����ꍇ�Ɂu�蓖������E�ܗ^�v��Ԃ��Ƃ����m�͈�@�s�ׂƂ��Ė����ł��̂ŕԂ��K�v�͂���܂���B�@
�@�J���҂��d��Ȍ̈ӂɂ���Ђɑ��Q��^�����ꍇ�́A��Ђ͘J���҂Ɉ��̑��Q�����𐿋����邱�Ƃ͉\�ł����A���̏ꍇ�́A�J���҂���Ђ̋��K�����̂����Ƃ��A��Ђ̕��i�𓐓�����̏ꍇ�ł���A��ʂɋƖ���̃~�X�ɂ�鑹�Q�̏ꍇ�́A�J���҂ɔ����ӔC��₤���Ƃ͒ʏ�͂��肦�܂���B �J���҂ɂ��d��Ȏ��̓��ł��A���̎��Ȃ̑ԗl�A�x���\�́A�g�p�҂̊Ǘ��ӔC�ȂǑ����I�ɔ��f����܂��B���ᓙ���݂Ă������z�͂��Ȃ菬�������̂ɂȂ��Ă��܂��B
�@�܂��āA�R�����Ԃ̌��N�ی��A�����N���̖@�l�ܔ��������x�����Ȃ��Ȃǂ͘_�O�ł��B���ɘJ���҂ɔ����ӔC�������Ă���ꍇ�ł��A�Љ�ی��ȂǂƂ͑S�����i���قȂ�܂��̂ŁA�x�����K�v�Ȃǂ���܂���B
�@�܂��A���C���̓������x�����K�v�͂���܂���B
�@���́u�m�F���v�u���v���̂���@�ł��̂ŁA�J���҂��T�C�������Ă��Ă��Ȃ��@�I���������������ƂȂ�܂��B�����S�������B
0415�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
| ���ސE���̃g���u���� |
Q: �@�����i�Ɂu���N�����ς��i�P�Q���R�P���j�v�őސE�������Ɛ\���o�܂����B�����Ė{���A�o�c�҂���u��������̋��l���o��������A���܂莟�掫�߂ė~�����B�x���Ƃ��P�Q���P�O�������ɂ͎��߂Ă��炢�����B�v�Ɠ`�����܂����B���̏ꍇ�A�u�ސE�v�ɂȂ�̂ł��傤���B����Ƃ��u���فv�ɂȂ�̂ł��傤���B�u���فv�̏ꍇ�A���ٗ\���蓖���W���Ă���̂ł��傤���B�ސE��A�ސE�͂͒�o���Ă��܂���B��i�Ɍ����œ`�����i���k�����j �����ł��B�u�P�Q���P�T���ɏܗ^�x��������̂ŁA���̑O�Ɏ��߂��������������v�Ƃ̃E���T������Ƃ̂��Ƃł��B
A: �@�u�ސE�������Ɛ\���o�܂����v�Ƃ̂��Ƃł����A���ꂪ�u�ސE�́v�ł͂Ȃ��P�Ȃ�u�ސE�肢�v�u�ސE�̑Őf�v�ł���ꍇ�ɁA��Ђ��Ɩ�����p�̓s���őސE������Ђ���]����������u�Őf�v���Ă��邱�Ƃ͈�ʘ_�Ƃ��Ă͍l�����܂��B
�@�������A���@�̋K��i�Q�T�ԑO�j��I�ƋK���Ɋ�Â��Đ����ȁu���������t�ސE�́v���o���Ă���ꍇ�ɁA��Ђ��ސE��F�߂Ȃ��Ƃ��A��Ђ�����Ɉ���I�ɑސE�������߂ċ��s���邱�Ƃ͋�����܂��A�����܂ŋ��s�������̏ꍇ�́u���فv�ƂȂ�܂��B���R���ق̏ꍇ�́A���ٗ\���蓖���͊W���Ă��܂��B
�@�܂������ȉ��ق̏ꍇ�́A�u�����ȉ��ٗ��R�v��K�v�Ƃ��܂��B
�@�J���_��@ 16 ���̋K��ɂ��A�q�ϓI�ɍ����I���R�������A�Љ�ʔO�㑊���ł���ƔF�߂��Ȃ��ꍇ�͌����̗��p�Ƃ��ĉ��َ��̂������ɂȂ�܂��B�܂��A�ƋK���̉��َ��R�ɊY�����Ă��Ȃ����R�̂Ȃ��s���ȉ��ق͉��ٌ��̗��p�ƂȂ�A���̉��ق͖����ƂȂ�܂��B
�@�@�u��������̋��l���o��������A���܂莟�掫�߂ė~�����B�x���Ƃ��P�Q���P�O�������ɂ͎��߂Ă��炢�����B�v�Ƃ̂��Ƃł����A���̉�Б��̔������u���فv�Ȃ̂��u�ސE�����i��Б�����̎��߂ė~�����Ƃ̒P�Ȃ�Őf�E��]�B�J���ґ��͋��ۂł���j�v�Ȃ̂�����Б��Ɋm���߂�K�v������܂��B�P�Ȃ�ސE�����̏ꍇ�ŁA 12 �� 31 ���őސE�������ꍇ�́A���R���ۂł��܂��B
�@�@�u��Ђ̂˂炢���P�Q���P�T���ɏܗ^�x��������̂ŁA���̑O�Ɏ��߂��������v�Ƃ�����A�܂��܂��u���فv�Ȃ̂��u�ސE�����v�Ȃ̂��ǂ������m���߂Ă݂��炢�����ł����B
�@�����āA�{�C�� 12 �� 31 ���őސE�������ꍇ�́A�u 12 �� 31 ���t���ސE�͂��i�u�肢�v�ł͂Ȃ��j�v�𐳎��ɒ�o���邱�Ƃ��܂��K�v�ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�Ȃ��A�L���x�ɂ��c���Ă���ꍇ�͑ސE���ɂ��Ă͂܂Ƃ߂Ď擾���邱�Ƃ��ł��܂��A���̏ꍇ�͑ސE�������̕��x�点�邱�Ƃ��ł��܂��B
0416�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
| ���������Ⴄ���炷���Ɏ��߂����� |
Q: �@�Ƃ��鋁�l�T�C�g���琳�Ј��̋��l�ɉ��債�܂����B
���p���Ԃ�6��������̂��C�ɂȂ�܂������A���ʂɂ���ΐ��Ј��ɂȂ��Ƃ������ƂőO�E��ސE���ē��Ђ��܂����B
���Ђ��Ă݂�Ƙb�ƈႤ���Ƃ����X���藣�E���������A�p���n���ɐ[��ɋy�Ԏc�ƁB
����̉ʂĂ�4������1�N�̌_��Ј��̏��ނ�n����܂����B
�ʐڎ��̘b�ƈႤ�Ƙb���܂������A�����Ƃ���Ă���ΐ��Ј��ɂȂ��ƌ����܂����A���ۂ͐��Ј��ɂȂ�Ă���l�͉c�Ƃł͖�E�҂�����3�l�����ł��B
�Ȃ�Ȃ����R�͎d���������Əo���ĂȂ��ƒ��ۓI�ȗ��R��������܂���B
���́A�ސE�������Ƙb�����܂������A���Ώo���邩��撣���Ăƈ������߂��Ă��܂��B
�ƈႤ�̂ł����ɑސE�������̂ł����A���Ȃ������ސE���邱�Ƃ͖@�I�ɉ\�ł��傤���H
A: �ŏ��ɓ��Ђ������ɁA�J�����������鏑�ނȂǂ�������Ă��܂��ł��傤
���H
�i������Ă��Ȃ��Ă��A�����Ă��炢�܂������H�j
�J�������̖����́A�J����@15���ɒ�߂�ꂽ�d�v�ȋK��ł��B
�����A���̍ŏ��ɖ������ꂽ������ƈ���Ă���̂Ȃ�A���̘J����@��15��2��
�̋K��ɂ���āA���Ȃ��̕����瑦���Ɍ_����������邱�Ƃ��\�ł��B
�u1�����玎�p����6�����v�Ǝ����Ă��āA4������1�N�̌_��Ј��̏��ނ�n���ꂽ�� �����_���|�C���g�ɂȂ邩�Ǝv���܂��B
���̓_�����Ƃɉ�Б��Ɖ������Č���i�߂�̂���낵�����Ǝv���܂����A
����l�ł͕s���Ȃ��Ƃ��������Ǝv���܂��B
�����ł����߂������̂��A�J���҂P�l��������ł���A�n�捇���J���g���i���j�I
���j�ւ̑��k������ł��B
�����ł́A���Ȃ��̂����k�ɂ������Ă���鑼�A�������Б��Ƒ����ɂȂ����ꍇ��
���̎x�����s�Ȃ��Ă���܂��̂ŁA
���ЂƂ��������Ă݂Ă��������B
���k�ɖK��邾���ł��A�����ǂ���������Ă��炦�邩������܂���B
�撣���āA���������������܂��傤�B
�������Ă��܂��I
0417�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
| ���ސE�̐\���o�͎O�����O�Ɂc���̊Ԍ�������Ȃ����s���� |
Q: �@���Ј��ł��B
���T�̓y�j���ɁA���݂̐E��ɑސE�͂��o����\��ł��B
�����A�C������Ȃ̂��A�N���ɉ�Ђ̃��[�_�[�I�Ȑl�����ސE���Ă���A�o�c�ҕv�w������ɑސE�͎O�����O�ɓ`���邱�ƁA�Ƃ����|�������ė��܂����B
�u�ސE�͎O������v�Ƃ������Ȃ̂ŁA���̎O�����̊Ԃɕs���Ɍ�������鋰�ꂪ����܂��B
���ɁA�O��ސE�������́A�o�c�҂����̕�����u��������v�ƌ���ꂽ�����ł��B
�܂��A���̉�Ђُ͈�ŁA���^���ׂ������ł܂���B
A: �g�p�҂ƘJ���҂́u�ٗp�_��v������ł���A�ސE�́A���̌ٗp�_��̏I�����Ӗ����܂��B
�ސE�ɂ��ẮA���Ȃ��̂悤�Ȑ��Ј��Łu���Ԃ̒�߂̂Ȃ��ٗp�_��v����Ђƌ���ł���A���@�ŁA�ސE�͒�o��Q�T�Ԃ��Ă��̌��͂�������i�ٗp�_�I���A�ސE�ƂȂ�j�Ƃ���Ă��܂��B
�������A�R�������ސE���Ƃ���u�ސE�́v���o���ƁA����܂ł͓����Ƃ����ӎv�\�����������Ƃɂ��Ȃ�A�Q�T�Ԍo�߂�������Ƃ����Ĉ���I�ɏo�Ђ��Ȃ��Ƃ������Ƃ����ƂȂ�\��������܂��B
�Q�T�ԂƂ����̂́A�������ɑސE�������Ƃ����ꍇ�ɁA���̎|�́u�ސE�́v���o���āA�@�I�ɔF�߂�����̂�����ł��B
�ސE�\��҂̋��^������I�Ɉ��������邱�Ƃ͂��������ł��B
���������J�������̈��������ɂ͖{�l�̓��ӂ��K�v�ł��B
���������ɉ��獇���I���R���Ȃ����͔̂F�߂��܂���B
��������������ꂽ��A�s���{���J���ǂɐ\���o�āA��������⒲������߂邱�Ƃ��ł��܂��B
���̍ہA���^���ׂ��Ȃ��ƕs���ł͂���܂����A�����̋��^�x���z�̏؋���A�Ζ����Ԃ̎��ȋL�^�i�����Ȃǁj�ł��؋��Ƃ��Ė��ɂ͗��͂��ł��B
����͋Ζ��\�̃R�s�[�Ȃǎ茳�ɕێ����邱�Ƃ������߂��܂��B
0418�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
| ��1�N�_��������X�V�c2�T�ԂŎ��߂���H�� |
Q�L���J���_��̃p�[�g�ɂ��Ď��₳���Ă��������B
���̉�Ђł�4�N���O�ɁA1�N�_�������ňȌ㎩���X�V�Ƃ����`�ō��Ɏ���܂��B
���^���オ��Ȃ����ƁA�x�݂����R�ɂ��炦�Ȃ��A�܂��o�Y����������Ă��炦�邩�킩��Ȃ��Ƃ���ꂽ���Ƃ����������ŁA�����������J���������痣�ꂽ���A�V�����]�E����������E��\���`���܂����B
����Ɖ�Ђ́u4�N���O�ɏ������_�ɂ͑ސE�̏ꍇ��3�����O�ɐ\���o��v�Ə����Ă���̂Ō_��ᔽ�B���Q�����𐿋�����v�Ƌ����Ă��܂����B
�Ј��͎���l�������炸�A���p�������Ԃ������邩��3�����ł�߂��Ă͍���Ƃ̂��ƁB
�������A�V�����]�E��ł͈��p�����ԂƂ���1���������҂ĂȂ��Ƃ������Ƃł����B
���E�łȂ�Ƃ��A�o�������̂��Ƃ͂��邵�A�ސE���Ă��d���̃t�H���[�͂���Ɠ`�������̂́A��������Ă��炦���A3�����͂��Ăق����Ƃ����܂����B
�������A���Ƃ��Ă͏o�Y��������Ɠ������Ђɂ��肽���̂ŁA�V������������������Ƃ͒f��킯�ɂ͂����܂���B
�ǂ������炢���̂ł��傤���B
A�F����҂ł���M���̏ꍇ�́A1�N�_��̌_��Ј��Ƃ��Ď����X�V�����4�N���o�߂����J���҂ł��̂ŁA�ʏ�͖��@628���̋K��ɂ���Ă�ނȂ����R���Ȃ���Ό_����Ԗ����܂œ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���A���@629���̋K��ɂ��A�e�����҂ɑ��ē��@627���̋K�肪�K�p����鎖�ɂȂ�܂��B
627���̋K��ł́u�ٗp�͉��i�ސE�j�̐\���ꂩ��2�T�Ԃ��o�߂���ΏI������B�v�̂ŁA2�T�ԑO�ɑސE�͂��o����ΑސE�ł��܂��B
�ސE�͔͂z�B�ؖ��t�̓��e�ؖ��X�ցi�X�ǂōw���j�𗘗p���邱�Ƃ��m���ł��B
���Q�����𐿋����邱�Ƃ͓��R�ł��܂���B
���������A�_��Ј��ɂ��Ă������Ǝ��́A���������Ŋ��Ԗ����ɂȂ�ΑސE�����邱�Ƃ��o����Ƃ����o�c�҂̓s���ɂ����̂ł���A�J���҂̎g���̂Ă̑��ʂ�����܂��B
�����Ɍٗp�������Ȃ琳�Ј��Ƃ��Čق������͂��ł��B
�]���āA�M���͉������邱�ƂȂ��A�@�ɂ̂��Ƃ�A�ސE����悢�����ł��B
�������Q���肵�Ȃ��œ������I
�J�����k�̉����͘J���g���E���j�I���ŁI
����s�����S����ʓ����J�g�@�@
�����̑��S�����W���p�����j�I���@�@
���p���������k���W���p�����j�I����
�� �uNPO�@�l�J�����k�Z���^�[���x�����v�֓�����I
�\����_������]�X�^�b�t�Ɂ\
���T�[�r�X�c�ƒǕ��L�����y�[���̔��Ώ����ƃR�����g��W
�������}�K�w�����ŁE�W���p�����j�I���x���Q�B�w�ǖ���
���\�����݂�http://www.jca.apc.org/j-union/mail-magazine/ml.htm
���u���O�u�J�����k�Z���^�[�X�^�b�t���L�v�X�V���I�R�����g���}�@�@