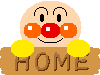労働相談Q&A
14 育児休業等
| <育児休業を取って復帰したら給料が下がった> |
Q:大手のスーパーで働いています。昨年から約一年間育児休業を取り、今年の 4 月から職場復帰しましたが、経営者から、しばらく ( 3ヶ月間 ) は前のようには仕事もできないだろうし、仕事の勘が戻るまでは、研修期間としてもらいたい。その間は給料を十分の一カットする」と言われました。法律ではどうなっていますか。
A:育児介護休業法の第 10 条は育児・介護休業をとった労働者への不利益な取り扱いを禁止しています。禁止する不利益取り扱いの具体的例として厚生労働省は告示 ( 第 13 号 ) で
1.解雇
2.正社員をパートに降格するような契約の禁止
3.減給や一時金の減額
4.自宅待機
5.不利益な配転等
をあげています。
本件のケースは明白な育児介護休業法違反となります。
1402
| < 育児休業が認められない > |
Q:正社員ですが、一年間の育児休業を申請したら復職は出来ないと言われた。
A:育児休業を申請し、または取得したことで会社が解雇したり復職を拒否することは重大な違法行為となります。
厚生労働省告示(平成 14 ・ 1 ・ 29 告示第 13 号)では、育児・介護休業法第 10 条及び第 16 条の規定による育児休業又は介護休業の申出又は取得を理由とする解雇その他不利益な取扱いの禁止に適切に対処するに当たっての事項として、以下を明記しています。
イ 解雇すること。
ロ 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと。
ハ 自宅待機を命ずること。二 降格させること。
ホ 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。
へ 不利益な配置の変更を行うこと。ト 就業環境を害すること。
1403
| <切迫流産> |
Q:切迫流産で長期に入院する場合、傷病休職としてもよいでしょうか?妊娠3ヵ月位で「切迫流産」となり、現在入院しております。とりあえず年次有給休暇を充てていますが、まもなく有給休暇もなくなります。当分入院が必要ということですが、当社規定では欠勤2週間経過後、休職になります。当社の規定では、休職事由が「傷病」か「自己都合」で休職期間が異なるのですが、どちらと解釈すればよいでしょうか。
A:正常分娩は傷病ではありませんが、「切迫流産」は健康保険の傷病手当金の対象となっており、傷病として扱われます。したがって、貴社の規定どおり、「傷病」に与えるべき休職期間を保障する必要があるでしょう。
正常な妊娠、分娩は傷病ではありませんが、健康保険法では、「切迫流産」のための療養が必要な期間については、傷病手当金の支給対象となります。
したがって、「切迫流産」のため休業(入院)し、有給休暇がなくなった以後、一定の欠勤を経て休職期間に入ったときは、「傷病休職」として取り扱う必要があるでしょう。
つまり、「傷病」による場合と「自己都合」による場合とで休職期間が異なるのであれば、「傷病」の場合の休職期間を保障する必要があるということです。
なお、「切迫流産」の治療の甲斐なく、もし流産(死産)となってしまった場合に、その流産(死産)の時期が妊娠4ヵ月( 85 日)以降であれば8週間(ただし、強制休業期間は6週間)の産後休業を与えなければなりません。
行政解釈では、「出産は妊娠4ヵ月以上(1ヵ月は 28 日として計算する。したがって、4ヵ月以上というのは、 85 日以上のことである)の分娩とし、生産のみならず死産をも含むものとする」(昭 23.12.23 基発第 1885 号)と明確にしています。
1404
| < 生理休暇を無くす会社 > |
Q: 男女雇用機会均等法があるから生理休暇をなくすという会社があると聞きましたが、これは違法にはならないのでしょうか。
A:均等法は、労働基準法に定める生理日の休暇や育児時間、産前産後の休業などの母性保護規定までを廃止したわけではありません。したがって、生理日の休暇は従前どおり、生理日の就業が著しく困難な女性労働者が請求したときには与えなければなりません。
男女雇用機会均等法は、募集・採用、配置、教育・訓練、昇進・昇格及び退職・解雇などで女性差別を禁止しています。労働基準法でも、女性の時間外・休日労働などの一般的な女性保護措置や深夜業に関する規制が原則として(妊産婦及び育児や家族介護を行う者を除く)撤廃されました。
しかし、生理日の休暇や育児時間、産前産後の休業などの女性保護 規定までが廃止されたわけではありません。したがって、生理日の就業が著しく困難な女性が請求した場合には、請求した日数の休暇を与えなければなりません。
なお、生理日の休暇中の賃金については有給・無休かはそれぞれの会社で決められます。
1405
| <育児時間と保育園への送迎> |
Q:保育園への送迎のための時間も育児時間として扱わなければなりませんか? 産休明けの社員が、保育園への子供の送迎のために、朝と夕方それぞれ 30 分ずつの育児時間をほしいといってきました。この場合にも育児時間として扱わなければならないのでしょうか?
A:満1歳未満の生児を育てる女性が請求した場合には、保育園への送迎時間も育児時間として扱わなければなりません。
労働基準法では、生後満1歳に達しない生児を育てる女性が請求した場合は、休憩時間のほかに1日2回、少なくとも 30 分ずつ、育児時間を与えなければならないこととされています。
育児時間は、労働時間の途中でも、あるいは始めや終わりでも、請求することができます。したがって、保育園への送迎のために、始業時刻を 30 分遅らせ、終業時刻を 30 分早めることを請求した場合も、それを育児時間として認めなければならないわけです。
また、育児時間を1回にまとめて、1日1回 60 分という形で請求することもできます。例えば、保育園に子供を預けるため、始業の時刻を 60 分遅らせるという方法などです。
なお、1日に2回、少なくとも1回 30 分という基準は、8時間労働を前提としたものであり、 1 日の労働時間が、4時間以内の短時間労働者の女性には、1日1回少なくとも 30 分与えればよいとされています。
1406
<勤務時間の短縮> |
Q:現在、育児の為の勤務時間短縮に関する措置を受けており、もうすぐ子供が1歳になりますが家庭の事情でもう1年とれないかと思っています。どうにかできないでしょうか?
A:平成14年4月1日より「勤務時間の短縮等の措置」が、従前の「1才未満」だけではなく「1才から3才に達するまでの子供を養育する労働者」に対して措置を講じなければならなくなりました。
ただし、講じる措置は以下のいずれかで良いことになっていますので、会社がどの方法を選ぶかにもよります。
(1) 短時間勤務の制度
(2) フレックスタイム制
(3) 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
(4) 所定外労働をさせない制度
(5) 託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
1407
<育児休業取得者に対する不利益取扱い> |
Q:現在、育児休業を取得中でもうすぐ復職する予定ですが、会社はいままでの雇用条件で復職させることはできないがパートならば復職できるといわれました。会社は、解雇はしていないので違法ではないといっていますが納得いきません。どうにかできないでしょうか?
A:平成13年11月16日より「育児休業の申出や取得を理由とする不利益取扱い」が、従前の「解雇を禁止」から「解雇その他不利益な取扱いを禁止」と変わりましたので、明らかな違法行為です。
不利益取り扱いとは、厚生労働省告示で以下の内容が明記されています。
イ 解雇すること。
ロ 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと。
ハ 自宅待機を命ずること。二 降格させること。
ホ 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。
へ 不利益な配置の変更を行うこと。
ト 就業環境を害すること。
1408
<有期雇用労働者の育児休業> |
Q:派遣社員として3年弱、現在の会社に勤務した後、会社都合により、5年を限度とする準社員に登用されて2年を過ぎた先日出産し、育児休業中です。育児休業給付金の申請をしたところ、対象条件の
1.休業開始時に同一事業主の下で1年以上雇用継続の実績があり、休業終了後同一事業主の下で労働契約が更新され3年以上雇用継続が見込まれる
2.休業開始時に同一事業主の下で3年以上雇用継続の実績があり、休業終了後同一事業主の下で1年以上雇用が継続することが見込まれること
上記1.にあてはまらないとのことで会社に却下されました。育休復帰後、「3年以上雇用継続が見込まれる」にあてはまらないためということです。私としては派遣時代も含めて8年近く勤務することとなり、雇用保険も払っているのに、育休を取得しても給付を受けられないことに納得いかないのです。アドバイスをいただけると助かります。
A:ご相談では「1.休業開始時に同一事業主の下で1年以上雇用継続の実績があり、休業終了後同一事業主の下で労働契約が更新され3年以上雇用継続が見込まれる 2.休業開始時に同一事業主の下で3年以上雇用継続の実績があり、休業終了後同一事業主の下で1年以上雇用が継続することが見込まれること」とのことですが、2005年の法改正で、有期雇用労働者にも育児休業法が適用されるようになっています。
法律では、
1,子が1歳に達するまでの育児休業(育児・介護休業法 5 条 1 項)は次のいずれにも該当する有期雇用労働者は、育児休業をすることができます。
1)同一の事業主に継続して雇用された期間が1年以上であること
2)子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること
となっていますので、会社の「3年以上雇用継続が見込まれる」云々はそもそも違法・不当と考えます。
2)に関しても「 3 年」ではなく「引き続き雇用」だけです。「見込み」はあくまで「見込み」ですので会社が育児休業給付金の申請を認めないことは明らかに不当です。
2,また「期間の定めのない契約と異ならない状態の有期雇用者」は、問題なく育児・介護休業の対象となります。
本件の場合も、
1)継続雇用を期待させる事業主の言動があった場合は、 2009 年まで契約の約束をしているのであれば、これに該当します。また派遣から準社員になった当時や育児休業を取る前に、会社から「来年も頼む」などの言動はなかったのでしょうか。
2)業務内容が正社員と変わらない同一の場合も、期間の定めのない契約とみなされます。本件の場合も派遣時代から5年間も勤務していますから、実際の業務内容は正社員と変わらないのではないでしょうか。
3,不利益取り扱いの禁止
メールを読ませて頂いた印象では、会社が嫌がらせでやってきている感じがします。育児・介護休業法第 10 条では明白に不利益取り扱いを厳しく禁止しています。厚生労働省は、法第10条及び第16条の規定による育児休業又は介護休業の申出又は取得を理由とする解雇その他不利益な取扱いとなる行為として下記の例を上げています。
イ 解雇すること。
ロ 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと。
ハ 自宅待機を命ずること。
二 降格させること。
ホ 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。
へ 不利益な配置の変更を行うこと。
ト 就業環境を害すること。
チ 有期期間雇用労働者の契約の更新をしないこと。
本件はこれに該当しないでしょうか。
さて今後のことですが、いくつかの道が考えられます。
会社があくまで拒否する場合は、ハローワークに強く求めて職権を発動させ、ハローワークに手続きをさせることです。
もう1つは、ひとりでも入れる地域のユニオンに加入して、会社やハローワークと交渉する道です。
もう一つの道は、労働局の雇用均等室に申し立てをする方法もあります。労働局で斡旋を依頼することもできます。
訴訟という方法もあります。この場合は、下記の弁護士の無料電話窓口でお尋ねください。
弁護士(日本労働弁護団)の無料電話相談窓口
日本労働弁護団 http://homepage1.nifty.com/rouben/soudan1.htm
電話 03-3251-5363 ・ 5364
毎週月曜日、火曜日と木曜日午後から3時から午後6時、
毎週土曜日 午後1時〜午後4時 *ただし土曜日は「03-3251-5363」のみ
●泣き寝入りしないで闘おう!
労働相談の解決は労働組合・ユニオンで!
<首都圏>全国一般東部労組
<その他全国>ジャパンユニオン
●継続した相談はジャパンユニオンへ
● 「NPO法人労働相談センターを支える会」へ入会を!
―矢部明浩さんを専従スタッフに―
●サービス残業追放キャンペーンの反対署名とコメント募集
●メルマガ『かわら版・ジャパンユニオン』月2回刊。購読無料
お申し込みはhttp://www.jca.apc.org/j-union/mail-magazine/ml.htm
●ブログ「労働相談センタースタッフ日記」更新中!コメント歓迎