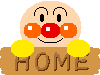労働相談Q&A
03解雇・雇止め
0301
| .<病気で3週間有給休暇で休んだら解雇された> |
.
Q: 健康不良で医者からしばらく休養するように診断されましたので会社に 診断書を提出し、3週間の病気欠勤と同時に有給休暇の申請をしました。
その時は、会社は快く認めてくれたのですが、3週間後に職場復帰したとたんに「健康上の理由で解雇」と言われました。
仕方がないのでしょうか。
A : 解雇の話と、復職の話とをまず切り分けて考える必要があります。
解雇については、労働契約法16条では「誰が見ても解雇はやむを得ないと考えられる理由がなければ、解雇は無効である」としています。
回復が難しく、実際に働くのも不可能もしくはあまりに難しい場合は解雇はやむを得ないとされる恐れもありますが、復職できたのであれば「健康上の理由」を解雇理由にするのは不当と考えられます。
また、有給休暇取得に対する不利な取扱い(解雇、賃金減額など)も労働基準法第136条で禁じられています。
休職期間終了後回復して働ける状態なのに解雇を言われた事例については、過去の裁判例(片山組事件・最高裁判決、平10.4.9)も法的な判断基準になっています。
この基準によると、特に職種が限定されてない労働者は、以前の仕事に復帰できなくても他の仕事で就労可能ならば、その仕事への配置の可能性を検討せずに解雇するのは無効、とされています。
労働者が回復していれば、現職が難しくても他の職務・配置転換などで解雇回避を図ったかどうかが問われたのがこの判決の本質です。
そもそもいかなる状況でも、解雇回避の努力を会社側が行っていない場合は解雇は無効、ともされているからです。
なお、復職および復職後の処遇については労働者の状態や意思、会社側の事情などを検討して協議する必要がありますが、労働契約法第5条では、労働者の生命や身体等の安全に配慮する義務(安全配慮義務)が会社側にある、と定めています。
少なくとも回復状態や治療、医師の助言を無視した労働環境に置かれないよう会社側に要求できます。
不当な解雇は会社側に撤回を要求できる可能性があります。
まずは都道府県の労働局、お近くの誰でもお一人でも加入できる地域ユニオンにご相談ください。
ただ、復職については法の規定・基準がないため民事の交渉ごとになりますので、地域ユニオンによる団体交渉が唯一有効な手段となります。
0302
| <精神障害者への差別> |
Q: 私は精神障害者手帳3級の者です。事務所でのデスクワークですが、最近 仲の良い上司に打ち明けたところ手の平を返すように冷たい仕打ちをして くるようになりました。昨日他の上司に呼ばれ「うちでは精神障害者は使えないから辞めてほしい。辞めない時は解雇するから」と言われました。
A: 明白な「精神障害者」に対する許すことの出来ない不当な差別です。
「障害者の雇用の促進等に関する法律」の第5条ですべての事業主は、障害者(身体または精神)の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、障害者である労働者が有為な職業人として自立しようとする努力に対して協力する責務を有するものであって、その有する能力を正当に評価し、適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならない」とはっきりと規定しています。
なお、同施行令9条により、雇用労働者の 1.8 %に相当する障害者の雇用も義務付けています。しかし、何よりも前に、精神障害を打ち明ける前は特段の問題もなく、普通に仕事をこなしていたと思われますので今回の退職強要は労働契約法 16 条の解雇権の濫用として違法と判断されます
このような上司、会社があることは大変残念なことですが、何らかの対応を取る必要があります。
対処方法として、公的機関を利用することができます。貴方の地域の労働局へ相談し、勧告、あっせん等を求めることができます。あっせん等で合意できなかった場合は労働審判を起こす方法があります。
他の選択肢としては1人でも入れる労働組合であるユニオンに加盟してその支援を受けて交渉することができます。ユニオンには憲法で保障されている団体交渉権などがありますので一番有効な手段と考えられます。会社側に謝罪、慰謝料、現職復帰などを求めて、粘り強く交渉しましょう。また、会社のなかに貴方を支援するような方がいる場合は一緒にユニオンに加盟するとより大きな力となります。
0303
| <実際は会社からやめさせられたのに自己都合退職とされた> |
Q: しつこい退職勧奨のあげく退職したのですが、会社から渡された離職票を見たら「自己都合退職」となっていました。失業保険は会社都合退職ならすぐに支給されるのに、自己都合退職の場合は3ヶ月も待たないと貰えません。なんとかならないのでしょうか。
A: 実態が退職勧奨などによって離職せざるを得なかった場合でも離職票に 「自己都合による退職」とされる場合が多数見受けられます。このような場合はハローワークに対して一般より有利な「特定受給資格者」として認定させることが重要です。相談者のような退職勧奨による退職は、自己都合による退職者よりも有利な「特定受給資格者」に該当します。
「特定受給資格者」とは、自己都合退職と異なり、3ヶ月間の待期期間がなく、かつ所定給付日数が多いことが特徴です。
手続きとしては、会社での離職証明書に「自己都合退職」と記入されていても、ハローワークでの雇用保険の申し入れの時点で離職票の異議欄に「会社による 退職勧奨の為」と記載し、「特定受給資格者」として 申し込みをします。出来るだけ下記の判断基準を立証できるものを添付・主張したらいいと思います。
「特定受給資格者」の判断基準には、次のようなものがあります。
1.倒産
2.事業所の縮小
3.事業所の閉鎖
4.事業所の移転による通勤の困難
5.解雇
6.労働条件が採用時と著しく相違している
7.賃金が二ヶ月以上にわたり三分の二しか支払われない
8.賃金が 85 %以下に切り下げられた
9.残業が月 45 時間以上(退職前3ヶ月間)続いた
10 .期間の定めがある契約更新を3年以上続けていたのに、契約が更新されなくなった
11 .上司・同僚から嫌がらせを受けた
12. 事業主から直接あるいは間接に退職勧奨された
13. 会社都合の休業が3ヶ月以上続いた
14. 事業所の業務が法令に違反している等があります。
0304
| <懲戒解雇だから明日から来なくていいと言われた> |
Q: 突然「懲戒解雇だから明日から来なくていい」と言われました。このようなことは問題ないのでしょうか。
A:懲戒解雇をする場合は就業規則や労働契約法等に基づいた正当な理由が必要になります。
第一に就業規則や法令に基づき正当に行われているか。また、懲戒解雇の理由が労働者の行為に見合っているか。
第二に手続きが適正であるかどうか(本人からの事情聴取や弁明の機会を与えたのか)等が必要になります。「突然」懲戒解雇だから来なくていいという経営者の一方的な懲戒解雇は法的には無効となります。
労働契約法 15 条では「懲戒が労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、権利の濫用として無効とする。」と規定されています。
0305
| <「経営が苦しい」から解雇!泣くしかないのか?> |
..
Q:社長から、経営が苦しいから人員削減のため解雇と言われた。同族経営の役員には多額の報酬を払っている。新規に新入社員も雇ったばかりだ。経営状況の中身の説明もない。会社は整理解雇と言っている。このようなやり方って合法なのでしょうか。
A:オーナー会社等によく見受けられますが、全く合法とはいえません。
「整理解雇」については、判例により確立されている整理解雇の4要件といわれる4つの条件がすべて備わっていないと「会社の解雇権の濫用」 1 として 解雇は認められません。4つの要件とは以下のとおりです。
(1)経営上、人員削減に高度の必要性が存在すること。
(2)解雇を回避するための努力が尽くされていること。
(3)解雇される者の選定基準と選定が合理的であること。
(4)解雇に至るまでに労働者、労働組合に誠実に説明・協議をしたこと
この内一つでも欠けていれば、整理解雇は出来ません。貴方の場合も、社長の解雇理由は全く不法行為であることはおわかりでしょう。対処方法として、公的機関を利用することができます。貴方の地域の労働局へ相談し、勧告、あっせん等を求めることができます。あっせん等で合意できなかった場合は労働審判を起こす方法があります。
他の選択肢として職場の仲間に呼びかけて労働組合を 立ち上げるか、地域の1人でも入れる労働組合であるユニオンに加入して解雇撤回を求め会社と交渉する方法があります。ユニオンには憲法で保障されている団体交渉権などの労働三権がありますので、一番有効な手段になると思います。
0306
| <「労災」で解雇!どうしても納得できない> |
Q:労災と認定されて自宅で療養していましたが、完治の見込みがないとして解雇されました。どうしても納得できません。
A:労基法19条1項は、使用者は、労働災害の休業期間中及びその後30日間は労働者を解雇できません(通勤災害は、労災保険給付はありますが、解雇制限にはなりません)。従って、完治の見込みがないとして解雇することは法律違反になります。
ただし、例外として、療養が3年たっても傷病が治癒しない場合、使用者が平均賃金の 1200 日分の「打ち切り補償」を支払った場合、あるいは傷病補償年金を受けている場合は解雇制限は解除され労基法には違反しません。
なお、安全配慮義務(労働契約法 5 条)違反があれば、債務不履行を理由とする損害賠償請求ができます。
0307
| <「病気で休業」で解雇!従うしかないのか> |
Q:二ヶ月ほど病気で会社を休みました。復職後、もう会社にこなくていいと言われました。従うしかないのでしょうか。
A: 労災の場合の解雇は禁止されていますが、私傷病による病気欠勤の扱いは、就業規則の決まりに従うことになります。
就業規則で「一定期間」の病欠が退職事由となっていればその解雇は認められることになります。
しかし、就業規則の退職事由に該当しないのにこのように解雇された場合ですが、休職後の復職時点で業務に支障がないのであれば、当然解雇は無効です。また、復職後の健康状態が今までの就労に支障がある場合でも厚労省の指針により、復職のための復帰支援プログラムの作成義務などによる、労働者への復職への支援が課せられています。
従って、就労可能な他の職場への配転を検討したのかどうかなどが解雇権濫用の判断基準となります。
以上より、解雇権の濫用として無効と判断されると考えられます。
0308
| <パートの更新が拒絶され雇い止めと言われた> |
Q:パートの更新が拒絶され雇い止めと言われた。三ヶ月契約で4回更新していたのに、次回はしないと言われた。あきらめるしかないのか。
A:4回も更新していた場合は、労働契約法第19条第1号に基づき「実際は期間の定めのない契約」となり、会社の一方的な「雇い止め」は、解雇と同等な扱いがなされ、許されていません。
従って、今回の雇止めは違法であり、契約は更新されなければならないものと判断されます。
0309
| <売り上げ実績が悪いからクビ?> |
Q: 営業マンですが、「全然売り上げ目標に達していない」といわれ「就業規則の勤務成績が著しく不良の時」という条項に該当するからと解雇されそうです。売り上げが上がっていないからあきらめるしかないのでしょうか。
A: 会社の一方的な解雇については、厳しい 制限がされています。労働契約法 16 条の規定により「客観的に合理性が理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は解雇権の濫用として無効」になります。
基本的に解雇は出来ないということです。貴方のようなケースの場合も労働契約法に従い、解雇理由が有効になるのは、営業中にサボっていたとか、上司の適切な指導にも拘らず長期に渡って成績が改善せず「勤務成績が著しく不良」な場合のみでしょう。
しかし、そのような場合でも、就業規則の勤務成績が著しく不良の程度 を検証する必要があります。ノルマの設定自体が高すぎる場合もあるし、販売する「商品」自体に問題がある場合もあります。このような場合は当然解雇権の濫用になります。
いざという時のため、常日頃から、反論できる資料(営業日報など)を整理しておきましょう。その上で、ユニオン(一人でも入れる労働組合)に 加盟して会社と交渉することが有効な手段となるでしょう。
0310
| <「リストラ」を理由に解雇を通告されました> |
Q:会社から「リストラ」を理由に解雇を通告されました。どう対処すればいいのでしょうか。
A : 会社が解雇を通告すれば一方的に何でも解雇が通用するものではありません。解雇には厳しい制限があります。「リストラ」つまり整理解雇については、判例により確立されている整理解雇の4要件といわれる4つの条件がすべて備わっていないと「会社の解雇権の濫用」として 解雇は認められません。4つの要件とは以下のとおりです。
(1)経営上、人員削減に高度の必要性が存在すること。
(2)解雇を回避するための努力が尽くされていること。
(3)解雇される者の選定基準と選定が合理的であること。
(4)解雇に至るまでに労働者、労働組合に誠実に説明・協議をしたこ と
上記の4つの要件をすべて満たしてはじめて整理解雇の正当性を持つのです。もし、上記の4要件が一つでもかけている場合は違法となります。
対処法については、 0305 を参照して下さい。
0311
| <突然「辞めてくれないか」と言われた> |
Q:上司から突然、「辞めてくれないか」と言われ、頭が真っ白になりました。どう対応したらいいのでしょうか。
A:まず「辞めてくれないか」の内容を会社側に明らかにさせる必要があります。「退職勧奨(会社からの合意退職の申し入れ)」なのか、「解雇」の通告なのかによって、こちら側の対応は違います。「退職勧奨」であれば、退職の申し入れですから、辞めたくなければ「辞めるつもりはありません。」ときっぱりっと断ればよいことです。「解雇」通告の場合は労働契約法 16 条の規定により「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は権利の濫用として無効」になります。
以上より、「正当な理由のない解雇は無効」なので、会社が一方的に解雇 を強行することはできません。まず解雇の具体的理由を書いた「解雇理由証明書」(労働基準法第22条で会社は提出義務がある)を提出させましょう。その上で争うかどうかを決めることがよいと思います。
0312
| <急に社長から解雇を通告されました> |
Q:急に社長から解雇を通告されましたが、納得できません。自分でも辞めるつもりですが、頭に来ています。何かよい方法はないでしょうか?
A : 正当な理由のない一方的な解雇は労働契約法 16 条の規定により、権利の濫用として無効になります。
解雇に納得できない場合は、貴方の地域の労働局で勧告やあっせんなどを求めることができます。それらが不調に終わった場合は労働審判を起こすことが出来ます。また、退職するつもりであっても解雇を争う場合は就労の意思表示を示しておくべきです。自ら、退職した場合は合意退職となり、事実上争うことはできません。
社長にとっては最善であり、貴方にとっては最悪の状況になります。 雇用保険の面でも損失を被ります。
他の選択肢はユニオン(一人でも入れる労働組合)に加盟し、その支援を受けて交渉する方法があります。ユニオンには憲法で保障されている労働三権があり、団体交渉することができます。もし、職場に同調する従業員がいれば、一緒に加入し、あるいは労働組合を立ち上げることが出来ます。ユニオンに加入することは労働者の権利を守り、労働条件などの改善が目 的ですので、退職してしまっては社長と争うことはできません。
それでも辞める気持ちでしたら、労働者を解雇する場合には30日前に通告する義務があり、その期間に満たない場合は解雇通告日から30日分以上の賃金を解雇予告手当として補償しなければなりません。
さらに未払残業代はないか、また年次有給休暇は完全消化しているかなどを調べ、もし未払であれば請求できます。また、退職時には残存する有給休暇は全部取得できます。
0313
| <試用期間が終わり解雇通告、解雇予告手当は?> |
Q:私は、入社3ヶ月で本日試用期間が終わり、明日から正社員として採用されるはずでしたが、先程上司に呼び出されて本日付で解雇を言い渡されたので、解雇予告手当を請求したところ、試用期間なので払う必要がないといわれました。 会社が言っていることは正しいのでしょうか?
A:例え試用期間といえでも、14日以上雇用されているのであれば予告手当を支払う必要があります。
なお、正当な事由なく解雇された場合は労働契約法に違反し、解雇権の濫用として、解雇は無効になります。貴方の地域の労働局に相談する事をお勧めします。
また、ユニオン(一人でも入れる労働組合)に加入し、会社側と争う事もできます。
0314
<契約期間満了による雇い止めは有効か?> |
Q:私は、今の会社に契約社員として4年6ヶ月勤務しておりますが、6ヶ月毎の雇用契約を更新して現在に至ります。しかし会社は、今回の契約切れをもって、契約更新はせずに期間満了による雇い止め(契約解除、解雇)を通告してきました。私は、会社の言う事に納得できないのですが、従わなければならないのでしょうか。
A:期間の定めがある雇用形態であっても、反復して契約更新がなされ、契約の更新が十分に予測できる場合には契約期間が形だけのものであり、実際は契約期間の定めのない労働者と同じ扱いであるという労働契約法第19条の規定に基づいて考えますと、あなたの場合、実態として期間の定めのない労働者に該当すると考えられますので、単に雇用期間満了に伴う雇い止めという理由では退職させる事はできず、解雇する場合には通常の正社員と同様に「正当な解雇理由が必要」になります。
今回のケースは労働契約法第16条違反として、解雇は無効と判断されると考えます。
従って解雇に従う必要はありません。
0315
| <解雇を通告されたが離職票には「自己都合」?> |
Q : 会社から解雇を通告されましたが、離職票には自己都合扱いとされていました。社長に確認をとったところ、「次の就職活動のことも考えて、君のためを思ってやったことだ」と言われましたが、本当に私に有利なことなのでしょうか?
A : 懲戒解雇というのであれば、就職活動に大きく影響する可能性はあるとは思いますが、通常の解雇がどこまで就職活動に影響するのかについては疑問です。ましてや昨今の世情をふまえ、リストラや倒産に伴う解雇が横行していることを考えると、逆に自己都合退職をすることイコール堪え性のない人間ととらえる会社も、当然のことながらあるのではないかと思います。つまり、面接を受ける会社の考え方次第で異なりますので、どちらが有利かなど判断できないのではないでしょうか。
面接の際に有利かどうかが分からないのであれば、雇用保険上も「特定受給資格者」(離職した日以前 1 年間に 6 ヶ月以上の勤務が必要)として失業手当の給付に 3 ヶ月の待期期間もなく、かつ一般の退職より所定給付日数が多くなる等優遇されます。解雇の方が就職活動全般を考えると有利ということになると思います。また、会社が「解雇」を嫌がる理由は違法行為であるため損害賠償などの請求をされるおそれがあること、会社の評判の低下、雇用助成金が貰えなくなる事などがあります。
また、「正当な理由のない」一方的な解雇は労働契約法 16 条の規定に 違反し、権利の濫用として無効であることも憶えておいて下さい。
0316
| <整理解雇についての要件・手続きは?> |
Q : 不況に伴う企業の経営不振による人員整理の場合に、一般的に裁判所は、整理解雇についてどのような要件なり手続きを要求しているのでしょうか?
A : 整理解雇については、客観的に見てやむを得ない事由のある場合に限り行うことが許容されるのであって、判例により、下記の4つの要件を1つでも欠いている場合は、解雇権の濫用として無効とされています。
1 ) 人員削減に十分な必要性がある。(企業が経営危機に陥り、企業の維持・存続を図るためには人員整理が必要で あること)
2) 解雇回避の努力を十分尽くしたか。(解雇に先立ち、希望退職者の募集、出向・配転その他余剰労働力吸収のた めに相当な努力が尽くされたこと)
3) 人選の公正・妥当性。(被解雇者選定のための基準そのものが合理的なものであり、かつその基準の運用も合 理的であること)
4) 労働者側との協議(整理解雇の必要性と人員削減の内容(時期・規模・方法)について、労働者、労働組合に誠 実に説明・狭義をしたか。
0317
| <解雇に対し何らかの補償を請求できないか?> |
Q:本日、いきなり「明日から出社に及ばず」という解雇通告を受けましたが解雇理由がはっきりせず納得できません。この様な事をする会社に未練はありませんが、何らかの補償を請求できないのでしょうか?
A:正当な理由のない一方的な解雇は労働契約法 16 条の規定により、解雇権の濫用として無効になります。理不尽な解雇に納得できない場合は、労働基準法 22 条 2 項の規定により、「解雇理由証明書」を使用者に要求することができます。その内容が法的にも 納得できない場合は、貴方の地域の労働局であっせんなどを受けることができます。あっせんが不調に終わった場合は労働審判を起こすことが出来ます。
また、退職するつもりであっても解雇を争う場合は就労の意思表示を示しておくことが必要です。自ら、退職する意思を示した場合は合意退職となり、事実上保障を要求して争うことはできません。
社長にとっては最善であり、貴方にとっては最悪の状況になります。また雇用保険の面でも大きな損失を被ります。
他の選択肢はユニオン(一人でも入れる労働組合)に加盟し、その支援を受けて交渉する方法があります。ユニオンには憲法で保障されている労働 三権があり、団体交渉することができます。もし、職場に同調する従業員がいれば、一緒に加入しあるいは労働組合を立ち上げることが出来ます。
なお、ユニオンに加入することは労働者の権利を守り、労働条件などの改善が目的ですので、退職してしまっては社長と争うことはできません。
それでも辞める気持ちでしたら、労働者を解雇する場合には30日前に通告する義務があり、即日解雇するような場合は30日分以上の賃金を解雇予告手当として補償しなければなりません。
さらに未払残業代はないか、また年次有給休暇は完全消化しているかなどを調べ、もし未払残業代があれば請求できます。また、退職時には残存する有給休暇は全部取得できます。
0318
| <うつ病で解雇?> |
Q: 大手スーパーの課長ですが、うつ病と診断され医師から3ヶ月の休業の診断書が出ました。
就業規則によれば、病気欠勤の休業は1年間認められていますので、会社に診断書を提出して病気休業の届けをしました。
一ヶ月休業して体調も戻り医師から一ヶ月に一度の通院を条件で復職の 許可の診断書ももらい総務に提出しましたが、総務は「もう病気でないのだから通院は必要ない」「精神病のスタッフがいるとわかればお客も離れる」「病気なら復職できない」「嫌なら退職しろ」と言われて困っています。
A: 解雇問題と復職の話をまず区別して考える必要があります。
勤務継続をご希望の場合、会社側から「退職しろ」と言われても応じる必要はまったくありません。
一方的に「解雇します」と言われていない限り、退職強要に応じる義務は法的にもないからです。
もし解雇だとしても不当となります。
解雇は労働契約法第16条により、誰が見ても解雇相当と考えられるような理由がない解雇は無効とされています。
また、休職期間終了後回復して働ける状態にあるのに解雇を言われた事例については、過去の裁判例(片山組事件・最高裁判決、平10.4.9)が法的な判断基準になっています。
この基準によると、特に職種が限定されてない労働者は、以前の仕事に復帰できなくても他の仕事で就労可能ならば、その仕事への配置の可能性を検討せずに解雇するのは無効、とされています。
そもそもいかなる状況でも、解雇回避の努力を会社側が行っていない場合は解雇は無効、ともされています。
したがって、退職強要については会社側に撤回を申し入れ、雇用継続を保障するよう交渉できます。
ただし、復職および復職後の待遇については、上記のような解雇に対する規制以外は特に決まった規定・基準がないので会社側との交渉が必要になりますが、留意点がいくつかあります。
主治医が復職許可を出していても、復職を最終的に決定するのは会社側です。
特に精神疾患からの復職については、労働者の実際の状態が良くないことを理由に会社側が復職を断る事例はしばしばあります。
うつ病は回復まで時間と慎重な対応を要するからです。
したがって率直に申し上げると、主治医が許可していても職務内容や労働環境を考えると復職に時間を要する、と客観的にも考えられる事情があれば、復職を延期せざるを得ないかもしれません。
しかし一方で、そうした根拠もなく復職を会社側が拒否してるのであれば、何をもって復職拒否としているのか根拠を追及してもいいと考えられます。
また、労働契約法第5条では労働者が健康や生命、人権が侵害されないよう職場環境に配慮する義務(安全配慮義務)を使用者に課しています。
これに基づき、健康状態や治療の経過に応じた労働環境への配慮を会社側はせねばなりませんので、主治医の助言、ご自身の状態に応じた配慮を求められる可能性もあります。
いずれにしても会社側との交渉は不可避と考えられますが、労働局か労働組合のご支援をご検討ください。
勤務継続の意思がおありでしたら労働組合(会社にない場合は誰でも一人でも加入できる地域ユニオン)が有効な手段となります。
特に、復職後の配慮が必要なのにメンタルヘルスに理解がない企業には、正しい知識をもって安全配慮義務を守るよう交渉で訴えかけていくしかないと考えられます。
0319
| <契約期間満了で雇い止め> |
Q: 月曜日に社長から突然解雇を言い渡されました。契約書には「解雇する場合は2週間前までに通知する」ということが記載されています。契約社員なので、契約期間満了といわれれば仕方ないと思っていますが、解雇理由は残業ができないからということでした。とても理不尽だと思います。何の問題もないのでしょうか?
A: 労基法第14条第二項を受けて厚労省告示による「有期労働者契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」が告示されています。それによると、以下のことが必要です。
1、労働契約の締結時にその更新の有無を明示しなければならない。
2.契約を 3 回以上更新し、又は一年を超えて継続している者に限り、契約を更新しない(雇い止め)場合には、少なくて も30日前に予告をしなければならないこと。
3.契約を更新する場合がある旨明示したときは、更新の有無についての判断の基準を明示しなければならない。
4.使用者は、労働者が更新しなかった理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。
5.契約を一回以上更新し、一年を超えて継続して雇用している労働者との契約を更新する場合は、労働者の希望に応 じて出来る限り長くするよう努めなければならない。
以上の法律に照らした時、今回の「解雇」には次のようないくつかの問題点があると思います。
1.契約書による2週間前の通知がなかったこと。また貴方が、契約更新が繰返され、一年を超えて勤務していた場合ならば 30 日前に予告がなされていないこと。
2.更新しない理由が明示されていないこと。
残業は労基法 32 条により、原則禁止( 36 協定を労使で締結している場合は残業も可能)とされていますし、その雇止め理由にも不当なものが認められます。
3.契約更新期待への配慮に反していること。
なお、雇い止めの理由を文書で求めることもできます。
また、そもそも労働契約法第19条により、相当期間にわたって契約が反復更新し続けられていれば、契約社員といえども実質的に期間の定めのない労働契約とみなされますので、今回の「雇止め」は通常の解雇に相当する可能性も否定できません。
以上より、今回の「解雇」は違法行為と考えられます。貴方の地域の労働局に相談することをお勧めします。最初にあっせん等を求めるといいでしょう。
より効果があると思われる方法は、職場に近いユニオン(一人でも加入できる労働組合)に加入して、会社と交渉することが出来ます。ユニオンには憲法で保障されている団体交渉権などの労働三権がありますのでかなり有効な方法となります。
0320
| <業務メールを会社側に「検閲・閲覧」されて懲戒処分> |
Q: 会社のメールを一度だけ私的に使用したことがあり、それが会社側に「検閲・閲覧」されて「俺を悪者にし、トップ批判したやつがいるから辞めさす」と解雇になりました。
メールの内容も「トップ批判」などしていません。
A: ネットの私的利用に対する企業・職場の検閲は、客観的に見ても正当な理由があり、労働者にそのことを事前に周知していれば、法的にも認められるとされています。
しかし、私的利用を理由とした解雇は場合によっては行き過ぎと判断される可能性も一方であります。
労働者には、そもそも職務に誠実に専念する義務があると考えられています(労働契約法第3条4項)。
また近年では、ウイルスや情報漏洩予防などのセキュリティー対策で、社員が不適切なサイトやネットのサービス(ファイル交換ソフトなど)を利用しないよう、ネットの利用状況を監視・記録するなど、私的利用に制約をかけている企業・職場が増えています。
ただし、こうした検閲行為は労働者のプライバシー権との兼ね合いも問われるものであり、旧労働省は「理由、実施時間帯、収集する内容を労働者に事前に通知し、個人情報保護の権利を侵害しないよう配慮するものとする」という指針を出しています(「労働者の個人情報保護に関する行動指針」2002年12月20日)。
したがって、検閲・調査を行うとする社内の規則(就業規則など)があれば、検閲自体は違法でもプライバシー侵害とも言い切れませんが、一方で解雇は「誰が見ても解雇は妥当と考えられるような理由がなければならない」とされているため、たった一度の利用で、しかもトップ批判をしていたという事実誤認があるとなれば、今度はこれが解雇相当なのかどうかが問われてきます。
そこで過去の裁判では、労働者も就業時間中に外部との連絡が一切許されていないわけではないこと、職務遂行の支障にはならず企業・職場側に過度の経済的負担にならないなどの限度を守っていれば、職務専念義務違反とはいえない、という判決が出ています(「グレイワールドワイド事件」東京地裁判決 平15.9.22)。
また別の判例では、使用頻度が多いので職務専念義務違反とされたものの、業務上の問題が出ておらず私的利用の黙認もあったことなどから、解雇は無効、とした判例もあります(「トラストシステム事件」東京地裁判決 平19.6.22)。
したがって、プライバシー権侵害については上記の通り、検閲行為の目的に正当性があれば不当とも言い切れないのですが、解雇の不当性は追及できる可能性があります。労働局、お近くの労働組合にご相談ください。解雇を撤回させたい場合は労働組合のほうが有効です。
| <形だけの取締役にさせられ、金までとられ解雇> |
Q: 会社から取締役の定数が足らないから役員になってくれと頼まれ、ほどなく経営危機だから資金をだしてくれと言われ、仕方なく貸しました。ところが7年半後、やはりやっていけないので解雇だと離職票を送ってきました。
A: 取締役の解任は会社法に従って、株主総会の開催によらねばなりません。 また、正当な理由がない場合、解任によって生じた損害について損害賠償請求ができます。(会社法 339 条の2)しかし、今回の場合は貴方が法的に実質的な取締役といえるのかが問題になると思います。
最大の論点は「取締役」に就任したという事実です。取締役といえば、経営者=使用者となりますので「労働者」とは対局にある概念になります。しかし、名称の如何に拘わらず、実質的に「労働者性」があるとなると、労働者として労働基準法(労基法)の適用を受けることが出来ます。
ご存じのように、労基法は会社などの使用者に雇用される労働者に適用さ れる法律です。取締役として、社長と一緒に会社の実質的な経営を担っているという実態が認められてしまうと、労働者性が否定されてしまいますから、労基法の適用を受けることはできません。
従って、未払賃金や退職金の支払を、労基法に基づいて会社に請求することは一切できないという結果になってしまいます。
まずは、ご自身経営者としての実態を有していたか確認してみる必要が あるでしょう。タイムカードや出勤簿で勤怠管理をされない「重役出勤」はしていたか? 給料を、労働の対価である「賃金」ではなく職務執行の対価としての「役員報酬」として受け取っていなかったか? 残業代は付いていたか? など…。
貴方の場合は取締役の定数(3名)に足りなかったため「労働者性」はそのままにして、役員とは名ばかりで実質は労働者であると判断されると考えられます。
給与明細にも「基本給」との名称で記載されている事実、さらには離職票」が発行されている事からも労働者であると云えるでしょう。
離職票が発行されたということは、雇用保険に加入していたということに なりますので、労働者性を主張するのに十分かつ決定的な材料になりえます。「労働者性」が認められれば、未払賃金と退職金の請求はできることになります。
また、労働契約法 16 条違反として、正当な理由のない解雇は解雇権の濫用として無効になります。
会社への貸付金についてですが、これは賃金債権ではありませんので、改めて裁判を提起して返済を求めることになります。
なお、今回の件は微妙な点もありますので一度下記の弁護士へ相談するこ とをお勧めいたします。
又、一人でも加入できる労働組合(ユニオン)に加盟し、その助力を受けて交渉することも有効な方法になります。
日本労働弁護団
電話 03-3251-5363・5364 毎週月、火、木曜日午後3時〜午後6時
毎週土曜日 午後1時〜午後4時 *ただし土曜日は「03-3251-5363」のみ)
| <内定の取り消し> |
Q: 11 月下旬になって、内定していた会社から業績赤字を理由に内定取り消しという簡単な電話連絡がきました。詳細は後日連絡するとのことでした。 あまりに突然だったので、抗議も何もできませんでした。私は何ができるのでしょうか。教えてください。
A: 内定通知された時点で企業との労働契約は成立しています(口頭での内々定を含む)。
従って、「内定取消し」は、すでに成立した労働契約の一方的解約(解雇と同じ)なので、労働契約法 16 条「解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は権利の濫用として無効とする。」が適用され、取り消すことは出来ません。
また、不況を理由とする内定取り消しの多くは合理性が認められません。企業の経営・人事計画にもとづいて積極的に募集しておきながら数ヶ月後に覆すほどの経営悪化は通常考えられないし、仮に経営が悪化したとしても、それを予見できなかった責任は会社側にあるからです。
厚労省は『新規学校卒業者の採用に関する指針』( H21 年 1 月 19 日改正)で不況を理由に内定取り消しをしないよう企業に指導しています。
従って、合理的な理由もなく「不況」を理由に契約を一方的に破棄することは違法で、効力がありません。企業に契約の履行や損害賠償を求めることができます。
そのためには企業から内定取り消しの連絡があっても「分かりました」などと同意と受け取られる発言はしないことです。
内定通知書や企業側とのやり取りのメモなど、労働契約が成立=内定したことを証明できる証拠を集めて交渉しましょう。
その際にはお近くにある1人でも加入できる労働組合(ユニオン)に加盟し、その支援を受けて交渉することをお勧めします。きっと貴方の力になってくれると思います。
| <PIP(業務改善プログラム)の結果を理由に解雇されそう> |
Q:米国系外資に買収された企業の日本子会社に勤めています。
日本子会社内で私だけPIP(Performance Improvement Program 業績改善プログラム)を行うよう所属部署の部長より言い渡されました。
内容が書いていない英文のA4の紙を見せられただけで改善内容も自分で考えるようにとのことでした。
退職勧奨はされていないので被害妄想で考えすぎだとは思うのですが、退職勧奨への導入なのでしょうか。
A:PIP(業績改善プログラム)が会社でどのような意味をもつのか、想像を膨らませると退職勧奨(解雇)に向けての試金石の可能性もあるでしょうし、買収によって新しい会社に生まれ変わるために米国
系外資企業の社風に合わない従業員を対象にして、意識改革を目的として行わせているのかもしれません。
メール内容だけですと想像の域をでませんが、あなただけに課せられていることに着目すると、感じている雰囲気からしてもペナルティーの要素がありそうですので、まずは退職勧奨が具体的に始まった場合に、どのように対処するか検討していきたいと思います。
自由な意思決定ができる状況になければ、不当行為である退職強要や実質的な解雇ということになりますので、仮に、PIP(業績改善プログラム)を作成して、その評価を理由として退職を迫る様なことがあれば、退職強要になります。
そのような可能性があるから、上司の指示であってもPIPは作成しないということになると、逆に会社からの指示命令違反で懲戒処分の口実を与えてしまう可能性がありますので、PIPの作成自体はやむを得ないのではないかと思います。
ただ、PIPの作成を繰り返し指示されたり、客観的に明らかに業務とは関係なく意味のない内容であって強要されるようなことがあれば、パワハラに該当する可能性もありますので、PIPの作成がどのような態様であるかによって、今後の対応を検討していく必要もあります。
今後のことについてですが、会社があなた自身に問題があると主張して、退職を迫る様なことがあっても、退職勧奨には応じない意思表示は明確にしておいてください。
会社が解雇に傾くようであれば、原則として就業規則に規定された解雇事由に限って認められるものになります。
労働基準法第89条では、就業規則には必ず「解雇の事由」を含めなければならないと規定されていることから、解雇を通告されたときには、就業規則上の根拠を明らかにさせることが重要です。
また、退職勧奨の体裁を取りながらも、会社に残る選択肢が用意されていない状況であれば、実質的に解雇ということになりますので、退職勧奨か解雇なのか確認する上でも、労働基準法第22条第1項の規定に基づく、解雇理由の証明書を要求してみてください。これは解雇に対抗する有効な手段となります。
会社としては上記の解雇要件をあてはめようとしますので、労働能力や適格性の欠如などを理由にすることが多いようですが、それらの解雇理由は客観的に会社側が証明する必要があり、例えば、前提として公平な評価制度があって、直近2年間が最低ランクで評価されていて改善する機会を与えているにも関わらず、改善できる見込みがない等の客観的な判断材料が必要になります。
ですので、PIP(業績改善プログラム)をいきなり導入して、短期間で低い評価を与えてその評価を理由にして解雇するようなことは、判例を踏まえるとその解雇は無効とされる可能性が高いので、解雇に対抗することは十分に可能と考えられます。
今後、段階を踏まえて退職勧奨から実質的な解雇に近づいてくる雰囲気がでてくるようなことがあれば、退職勧奨には応じない意思表示を明確にした上で、この退職勧奨は実質的には解雇であって、解雇理由の証明書等に依拠しても解雇に合理的な理由はなく、社会通念上相当であると認められないものとして、無効であることを主張することが交渉を有利に進める上で重要です。
対処法ですが、まずは都道府県労働局(厚生労働省の地方出先機関)で、退職勧奨の不当性や解雇理由がないことを主張することができます。
労働局からの指導や勧告によって、会社があなたへの対応を改める方向に変化するかもしれません。場合によっては紛争調整委員会に斡旋を行わせることもできます。
会社が退職勧奨を繰り返してくる状況になると、個人で対応することが精神的にも大変になりますので、以上のような制度を利用していただき、また、長期戦になるようであれば、身近な応援団として、専門的な意見やアドバイスをしてもらえる労働組合に加入されることをお勧めします。
さらに、労働組合に加入することにより交渉力が強まれば、会社は相応に対応しなければなりませんので、状況を改善させることができるかもしれません。
労働組合と接点がない又は既に加入している労働組合があっても相談しづらいようであれば、日本全国どこからでも個人で加入できる「ジャパンユニオン」への加入をお勧めします。以下、ホームページのURLです。
http://www.jca.apc.org/j-union/
PIP(業績改善プログラム)の作成でめげることなく、今後、例え退職勧奨や解雇の方向性が明確になっても、既述の様々な手段を利用すれば会社に十分に対抗でき、解決する方法もでてくると思います。
●泣き寝入りしないで闘おう!
労働相談の解決は労働組合・ユニオンで!
<首都圏>全国一般東部労組
<その他全国>ジャパンユニオン
●継続した相談はジャパンユニオンへ
● 「NPO法人労働相談センターを支える会」へ入会を!
―矢部明浩さんを専従スタッフに―
●サービス残業追放キャンペーンの反対署名とコメント募集
●メルマガ『かわら版・ジャパンユニオン』月2回刊。購読無料
お申し込みはhttp://www.jca.apc.org/j-union/mail-magazine/ml.htm
●ブログ「労働相談センタースタッフ日記」更新中!コメント歓迎